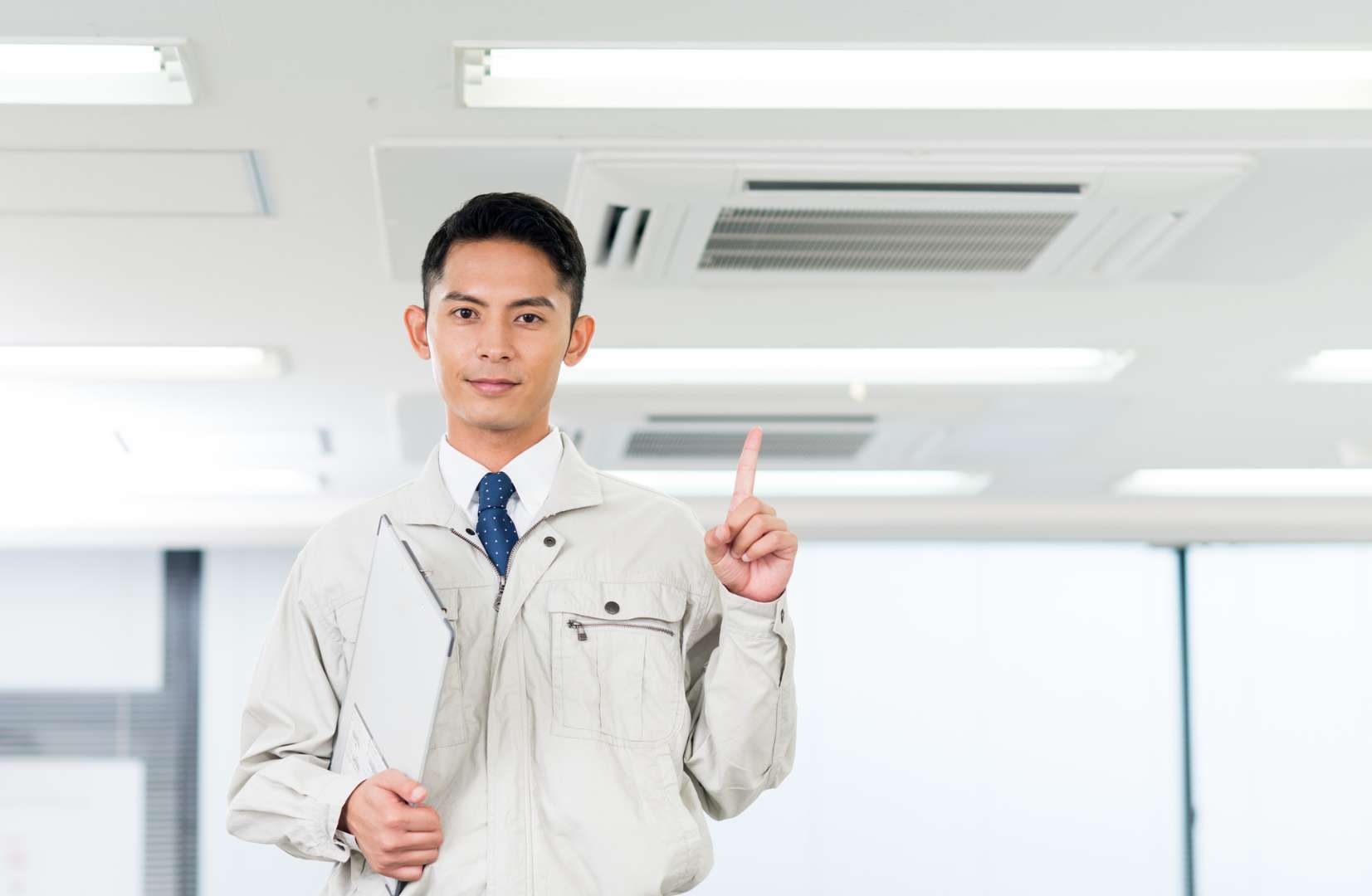コンクリート工事と聞いて、どんな風景を思い浮かべるでしょうか。生コン車が現場に入り、流し込んだコンクリートが職人の手によってならされていく──そんな一場面を思い浮かべる方も多いかもしれません。けれど実際には、その裏側にたくさんの段取りや専門技術が詰まっています。建物や構造物の土台をつくるこの仕事は、「ただ固める」だけでは成立しません。地盤の状態や設計図に応じて、段階ごとに役割分担された作業が続いていきます。中でも大切なのは、すべての工程に“流れ”があるということ。ひとつでも抜けると、仕上がりに大きく影響するのです。この流れを理解することは、現場に入る前の第一歩。今回は、これから現場を目指す方や業界に興味を持つ方へ向けて、コンクリート工事の一連の流れをわかりやすく整理していきます。特別な経験や知識がなくても大丈夫。まずは、どんな工程で成り立っているのかを知ることから始めてみませんか。
工事の最初はここから|準備・型枠設置・配筋作業の役割と注意点
コンクリート工事は、コンクリートを流し込む前の準備段階がとても重要です。現場に立ってすぐに打設(だせつ)できるわけではなく、下地づくりが丁寧に行われているからこそ、後の工程もうまくいきます。まず行うのが「墨出し」と呼ばれる作業です。これは図面に基づいて、実際の現場に寸法や高さの基準線を引く工程で、すべての作業の基準となります。
その後、型枠と呼ばれる“枠”を組み立てていきます。この型枠が、コンクリートの形状を決める大事な器です。水平や垂直が少しでもズレていると、後の構造に大きな影響が出るため、ミリ単位での確認作業が必要です。さらに、打設時の圧力にも耐えられるよう、しっかりと固定しなければなりません。
型枠が組み終わると、鉄筋を配置する「配筋(はいきん)」作業へと移ります。鉄筋はコンクリートの“骨”のようなもので、引っ張りや曲げに強い構造をつくるうえで不可欠な存在です。図面通りの位置に、決められた本数と間隔で設置していく必要があります。ここでも、ただ置くだけでなく、結束線で確実に固定するなどの細かい配慮が求められます。
この準備工程は、いわばコンクリート工事の“土台作り”。見えにくい部分こそが、建物の寿命を左右するのです。ひとつひとつの作業が丁寧であるかどうかが、その後の品質を大きく左右します。
いよいよ打設作業|流し込みから養生までの一連の流れ
型枠と鉄筋の準備が整うと、いよいよコンクリートの打設に入ります。現場では「打設」と呼ばれますが、これはコンクリートを型枠の中に流し込んでいく工程のこと。生コン車からポンプを使って運ばれることが一般的で、その際のスピードやタイミングは非常に重要です。あまりにゆっくりだと硬化が始まってしまい、逆に早すぎても均等に広がらずムラが生まれます。
打設中には「バイブレーター」と呼ばれる機械を使用して、型枠の中でコンクリートを振動させながら隙間なく行き渡らせていきます。これによって内部の空気を抜き、強度のある構造をつくることができます。ただし、振動が強すぎたり長時間当てすぎたりすると、型枠や鉄筋に悪影響を及ぼすこともあるため、現場の経験と感覚が必要とされます。
コンクリートが型枠にしっかりと行き渡ったら、次は「養生(ようじょう)」という工程に入ります。これは、コンクリートが十分な強度を得るまでの間、乾燥を防ぎながら適切な温度と湿度を保つ期間のこと。夏場は直射日光を避けたり、冬場は凍結しないように保温したりと、季節によって管理の方法が異なります。
この養生期間をおろそかにすると、仕上がりにムラが出たり、ひび割れの原因となったりします。たとえ見た目に問題がなくても、内部に目に見えない欠陥があることもあるため、表には見えにくいこの工程こそが、職人のこだわりと責任感が試される場面です。
安定した仕上がりのカギ|硬化・脱型・仕上げ作業とは?
コンクリートが型枠の中でじっくりと強度を高める「養生」期間を経て、次に行われるのが「脱型(だったい)」と呼ばれる作業です。これは、固まったコンクリートから型枠を取り外す工程で、強度が十分に出ていないうちに外すと、角が欠けたり表面が荒れたりといったトラブルが起こります。そのため、気温や使用したコンクリートの種類、設計強度などに応じて、脱型のタイミングは慎重に判断されます。
脱型後には、表面に残ったバリや不陸(凹凸)をならす「仕上げ作業」が入ります。これにより、見た目の美しさだけでなく、構造的な安定性も整えられます。特に外部に露出する箇所や、仕上げ材を使わない“打ち放し”仕上げの現場では、表面処理の良し悪しがそのまま建物の印象を左右するため、細やかな手作業が求められます。
また、構造物によっては、次の工程に進むための確認作業や強度測定を行うこともあります。たとえば、壁や床に続く内装工事に影響が出ないように、表面の状態や寸法のズレを確認しながら、次の作業との連携を図っていきます。ここでも大切なのは「流れ」を断ち切らないこと。前の工程でのズレやミスがあれば、必ず次の作業に影響します。
このように、コンクリート工事は「流し込んで終わり」ではありません。硬化から脱型、仕上げまでの細やかな確認と手入れを経て、初めて“完成”と呼べる状態に近づきます。外から見えない部分にこそ、職人の手仕事と責任感が表れているのです。
求められる技術とチーム力|現場での動きと連携の重要性
コンクリート工事は、ひとつの工程だけで完結する仕事ではありません。準備、打設、仕上げと段階ごとに進む中で、それぞれの職人が自分の役割を全うしながらも、周囲と呼吸を合わせていく必要があります。どれだけ技術があっても、タイミングや判断を誤れば次の工程に負担がかかる。だからこそ、この仕事では“チームでつくる意識”がとても大切になります。
たとえば、生コンの搬入ひとつをとっても、現場の誘導、ポンプ操作、バイブレーターによる締固めなど、同時に複数の動きが連携してこそスムーズに進みます。少しの遅れや確認ミスが、固まりかけたコンクリートという取り返しのつかない事態を招くこともあるため、常に周囲との声かけや状況把握が求められます。
また、若手や未経験者であっても「これは自分の作業だけじゃない」という意識を持てるよう、現場では先輩たちが積極的にフォローする風土があります。段取りや準備の背景を説明したり、声をかけながら作業の意図を伝えたりと、“教える”こともまた仕事の一部として捉えられています。
コンクリート工事は、単なる力仕事ではありません。全体の流れを読み、必要な動きに気づき、誰かと連携しながら動ける。そうした“現場力”が問われる仕事です。技術は後から身につけることができますが、この姿勢はどの段階にいても求められる基本姿勢といえるでしょう。
桑路建塗では、こうしたチームとしての仕事を大切にしながら、新しい仲間を迎える体制を整えています。未経験からスタートしたい方、技術と一緒に「現場での人との関わり」も学びたい方は、ぜひこちらをご覧ください。
▶︎ https://www.kuwaji.com/workstyle
「流れ」を知ることが、成長の第一歩になる
コンクリート工事の仕事は、目の前の作業だけに集中するだけでは本当の力は身につきません。全体の流れを知り、次に何が起こるのか、どこで誰と関わるのかを意識することで、一つひとつの作業にも意味が生まれてきます。準備から仕上げまでの道のりを理解することは、ただ教えられた通りに動くのではなく、「自分で判断し、考えて動ける」力につながっていきます。
最初は右も左もわからなくて当然です。ですが、この仕事は毎日現場に立っていく中で、自然と全体の流れが見えてくるようになります。その過程こそが、職人としての成長であり、信頼を得る力にもつながっていくのです。
そして何より、完成した構造物を見上げたときに「自分の仕事が、ここにある」と実感できるのは、何にも代えがたいやりがいのひとつです。自分の手が、地面にかたちを刻み、未来に残っていく。その手応えを味わいたい方は、まずは一歩、踏み出してみてください。